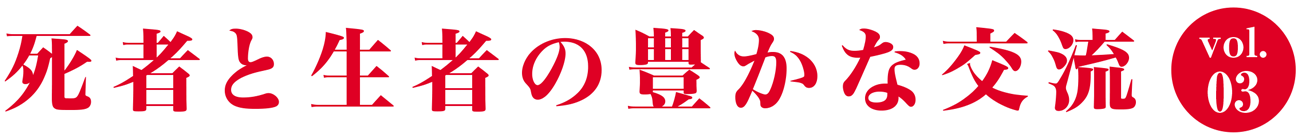
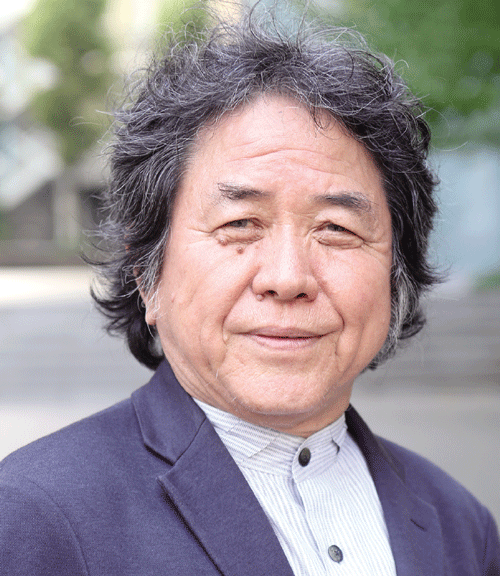
日本人の死生観、すなわち古来日本人が生と死をどのように捉えてきたかを探っていくと、どうしてもまた、日本人がどのような霊魂観や他界観を抱いて生きてきたのかを探らざるを得なくなります。民俗学などで、葬儀やお墓やお祭りに注目されるのは、そこにあの世とこの世、死者と生者の交流の場を、祖先たちがどのように構築してきたを垣間見ることができるからです。
古来、わが国では、死者の霊魂は残された子孫達の供養を受けることで昇華されると考えられてきております。初七日や四十九日に始まって、一周忌、三回忌などを経て、三十三回忌の弔い上げで、無事それまでの祖霊と合流し、カミ(一神教の神ではない)になって、今度は子孫を守護するようになると信じられて来たのです。
腸(はらわた)がちぎれそうな愛する者との別れ、浄土に到達できず、途中でさ迷っているのではないかという心配。情のことのか深い日本人は、死(者)を想い、生を紡ぎながら、途轍もなく美しい死者との再会・交流の場を生み出してきたのです。その一例を今号と次号でご紹介してみましょう。
毎年お盆が近づくと愛する人々が我が家に帰ってくるのを待ち受けて、ご馳走を用意したものです。迷わないように迎え火をたき、再会を喜び、数日を共に過ごし、やがて盆花とともに茄子で作った馬に乗せて、送り火たいて送り出すという古来の習俗。私が日本各地の万燈で出会った多くの母たち、父たち、妻たち、夫たち。一様に彼らは忘れられぬ“あの人”に、ここでなら会えると足を運んで来るのです。
2005年8月15日、私は有名な盆踊りを観るために、新幹線豊橋駅から飯田線を乗り継ぎ、さらにバスとタクシーに乗り、南信州の新野におりました。この祭りは大正年間末、当地を訪れた日本民俗学の創始者の柳田国男と折口信夫が、まだこんな美しい祭りが残っていたのか、と感動したということ。ずっと観たいと思いながら、相継ぐ障害のためやっと訪れた新野高原には、なにか魂の交流を伝統として守り続けてきた風土が感じられました。その時の祭りについて、紙数の都合から、今号と次号の二回に分けてご紹介してみたいと思います。
800メートルを超す高原とはいえ、やはり8月半ば午後の新野は暑熱の中、しかし、夜はぐっと冷え込むとのこと。思った通り、新野の宿はすべて満杯。仕方なく6kmほど離れた隣の売木村の民宿に、送り迎えしてくれることを条件に投宿しました。
しかし、この時点はその売木村で、鳥肌が立つような感動的な祭りに出くわすとは思いもよりませんでした。
翌朝のフィナーレに焦点を合わせた私は、夕食も済み、8時頃女主人の車で宿を出ました。同日は売木の村祭りも最終日で、彼女の話では、規模は新野と比較にならないが、とても素朴ないい祭りだというので、全く期待もないまま、しばし立ち寄ることにしました。
中学校の校庭の薄暗い灯火の中、踊っているのは三十人足らず。無論、屋台はなく、見物しているのは私のみ。しかし、その光景の美しさの奥には、この日を限りに別れゆく死者の影すら見えるようなのです。
やがて、9時過ぎに盆踊りは終わり、やぐらから吊り下がっていた六つの切子燈籠が切り下されます。つまり、その年に亡くなった村人は、その地区では六名だったというわけです。
ほどなく、精霊送りの列は校門の坂を下り、通りを村はずれを流れる川の方へと進んでいきます。両脇の家々の窓や戸が開かれ、踊りに参加できなかった老人や病人も姿をみせ、帰り行く精霊を見送るのです。
そして、石橋の上に燈籠が積み上げられ、最後の別れを惜しむかのように、またその回りをゆっくりとした歌に合わせて踊る人々の、その動きの優しさ美しさ。
やがて、燈籠の山に火が放たれると、勢いよく立ちのぼる炎と火の子。まさにたましいが天に帰っていく様を、体全体で感じている私の目にはいつしか涙が浮かんでおりました。私は思いました。こんな風に送られるのなら、いつ死んでもよいと。
ここには死者と生者の余りにも優しく、美しいたましいの交感がありました。生きていることと死んでいることは、この世界では何のちがいもありませんでした。まさに生と死とは一つつづきであったのです。
紙数が尽きてしまいました。新野の盆踊りについては次号で。
